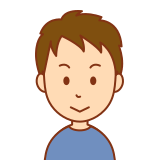
基本的なことをQ&A形式にしました。内容は正確性を期したつもりですが、お気づきの点があれば「POST]にお願いします

マンション関連法が改正された背景は?
今回の改正は「区分所有法」などマンション関係の法律を一括して改正するものです。
改正された背景には、築年数が経過したマンションの増加と、居住者の高齢化という「2つの老い」によって、このまま推移すると、更に深刻な事態になるという危機感があります。
深刻な事態とは、管理不全によって、建物の破損が放置され危険な状態になることや、極端な例ではスラム化などです。

「二つの老い」とはどういうことですか
現在は、建築後40年を経過したマンションが全体の2割であり、今後10年で2倍に、20年後には3.4倍になるといわれています。このまま推移すると、20年後には、建築後40年を経過したマンションが7割となり、世帯主が70歳以上の住戸が半分以上になる見込みです。建物、居住者、どちらも「老い」がすすんでいることが、マンションの「二つの老い」です。

「区分所有法」とはどういう法律ですか
正式名称は「建物の区分所有に関する法律」といい、1962年に制定されました。マンションの基本法というべき法律です。
マンションは1棟の建物の特定部分を「持ち家」とする住居形態ですが、その「持ち家部分」に「区分所有権」という特殊な権利を認めることによって、売買や抵当権の設定ができるようになりました。
この区分所有法がなければ、現在の分譲マンションという形態は存在しえないことになります。

区分所有法の歴史と今回の改正について教えて
区分所有法は、1962年(昭和37年)制定ですが、建物と敷地利用権の分離譲渡禁止が規定された1983年(昭和58年)改正によって、スタートしたといえるでしょう。
1962年(昭和37年)制定
区分所有法は、1962年(昭和37年)に制定されました。
民法208条には、建物の区分所有「数人にて1棟の建物を区分してその一部分を共有するとき」という条文があったのですが、区分所有法制定によって削除されました。
国の住宅政策が、集合住宅が増加するということを見越した立法であったといえます。
しかし、まだこの時点では、住宅公団による団地供給か主であった時代です。
1983年(昭和58年)改正
この改正で現在の区分所有法の原型ができました。
(1)区分所有建物と敷地利用権と専有部分の原則分離処分禁止
(2)区分所有者が当然に建物・敷地・付属設備の管理を目的とする団体を構成し、意思決定は多数決による
第1点の規定は、当たり前と思えるもので、これがないと分譲マンションは成立しません。
第2点は、管理組合に関する規定です。
2025年(令和7年)改正
2025年(令和7年)老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)が成立しました(同月30日公布)。
マンションの急増は、83年改正以後のことであり、80年代に建設されたマンションが、築40年を経過し、様々な問題が顕在化してきました。今起きている問題は、「起こるべくして起きた」といえます。これに対応するための立法が今回の改正です。

標準管理規約とはなんですか
標準管理規約とは、国土交通省が公表している「マンション標準管理規約」のことです。
ほとんどのマンションの管理規約は、これをモデルとして作成されています。2025年10月に、新しい標準管理規約が公表されました。
区分所有法は「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」としています。
管理規約に定めがない事項は、区分所有法の規定に従うことになります。

建物の「高経年化」とは、どういうことですか?
「高経年化」とは、建築後相当年数が経過していることですが、国の資料などでは「40年」を一つのメドとしているようです。
建築後40年を経過しても、管理が良好であれば、「老朽化」とはいえません。
ところが、管理不全のマンションでは、外壁の剥落などの危険な状態のものもでてきます。
管理不全が、おきる原因として、修繕のための区分所有者の合意が困難になっていることが、原因の一つと言われています。

「合意が困難」になっているとは、どういうことですか
マンションの外壁、外廊下、付属設備は、区分所有者の共有ですから、区分所有者の意見がまとまらないと、変更や修繕ができません。「決議」は区分所有者の集会(総会)で、なされます
一つの建物を「区分所有」するマンションは、意識の相違や多様な価値観を持つ人が、生活していることから、合意形成には、特有の困難があります。
「高経年化」から起きてくる困難さは、また別のものです。
建築後年数か経過してくると、区分所有者が、居住していない事例も相当数出てきます。
居住者の高齢化も大きな問題で、理事会が機能していないという問題も起きてきます。
今回の法改正では「出席者多数決」の採用、所在不明者対策が、盛り込まれました。
川口市マンション実態調査(平成30年)によれば、総会を「ほとんど開催していない0.7%」「数年に1回0.4%」というところもあるようです。

住民の高齢化は何が問題ですか
住民の高齢化はマンションに限ったことではありませんが、マンションの高齢化は、特有の問題があります。
マンションは1棟の建物一部を自分の「持ち家」としていますが、外壁、廊下、エレベータなど、多くの共用部分があります。これらの維持修繕は、他の区分所有者との合意が必要ですが、高齢者が多くなると、管理組合が、十分機能しない、様々な原因で、合意形成が進まず、必要な修繕が放置されるといった事態が起きがちです。

今回の改正で「所在不明者」について規定されたようですが
今回の改正で、区分所有法に、「所在不明者」についての規定が創設されました。
裁判所の認定が、必要ですが、所在不明の区分所有者を、決議の際、員数に入れないことが可能になりました。
これも、居住者の高齢化と関係しています。分譲から40年も経過すると、居住者が死亡する例も少なくありません。相続登記がなされないと、管理組合としては、区分所有者が不明という事態も起きてきます。
このような事例が多いことから、この制度が作られたものと思います。

Qマンションの管理規約の改正は必要ですか
新区分所有法が2026年4月施行されます。それにあわせて、2025年10月、新しいマンション標準管理規約が公表されました。
マンションの管理規約のうち、新法で改正された部分は、無効となります。
管理規約をそのままにしておくと、混乱の原因になりますので、改正をおこなったほうが、よいでしょう。

Q規約改定が間に合いません。改正しないとどうなりますか
管理規約の改正は総会決議事項です。2026年4月以後は、旧法に基づく規定は無効となります。決議要件などは、管理規約を改正しなくても、区分所有法の規定に従うことになります。
管理規約が古すぎる、現状に合わないということもあると思います。
法改正によって、管理規約の一部が無効になっている事を区分所有者に、お知らせした上で、管理規約全体の見直しを進めた方がよいと思います。
![]()

